2025.07.10
お葬式に湯灌(ゆかん)は必要か?必要性や手順・料金などを解説

大切な方を亡くした後、「湯灌(ゆかん)は本当に必要なのだろうか」と悩まれる方は少なくありません。通常のお清めだけで十分なのか、または湯灌を行うことで遺族や故人にどのようなメリットがあるのか、費用はどのくらいかかるのかなど、多くの疑問や不安を抱えているのではないでしょうか。
この記事では、湯灌とは何か、そしてお葬式のなかで必要とされる理由をわかりやすく解説します。
また、実際に湯灌を依頼する際の流れや注意点、料金相場なども取り上げますので、湯灌について気になっている方は、故人への最後のケアとなる湯灌について、ぜひ本記事を参考にしてみてください。
【そもそも湯灌(ゆかん)とは?基本的な意味と役割】

湯灌(ゆかん)とは、故人の体を温かいお湯で洗い清めることで、古くから日本の葬送文化に根付いている儀式です。
遺族や参列者は「最後まできれいな姿で送り出したい」という思いから、湯灌を大切に考えています。最近では葬儀会場だけでなく、自宅で出張サービスを利用しやすくなったことで、より多くの方に選択肢として検討されるようになりました。
湯灌の主な目的は、故人の身体を清らかな状態に整えることはもちろん、亡くなった方への敬意を示し、遺族が心を込めてお別れをするための重要なステップといわれています。
【湯灌が注目される背景と歴史】
湯灌は日本特有の習慣と思われがちですが、水や湯を使って身体を清める風習はアジア各国でも見られます。日本では特に仏教や神道が盛んに広がった江戸時代以降、湯灌が一般庶民にも浸透しました。
かつては「湯灌場」という専用施設まで存在し、地域で協力して故人を手厚く送ることが当たり前でした。
近年では家族葬や直葬など葬儀形態が多様化するなか、故人としっかり向き合える儀式として再び注目を集めています。高齢化社会に伴い看取りの機会が増え、「清らかに送りたい」という想いを形にしやすい湯灌が見直されているのも、背景の一つです。
【湯灌は必要か?行われる理由】
「湯灌は必ず行うべきなのか?」と疑問を感じる方も多いでしょう。結論としては、宗教や地域的な慣習、遺族の意向などによって変わります。ただし、湯灌を行う理由は大きく分けて二つあります。一つ目は、故人をきれいな姿で見送ることで、遺族や参列者が安らかな気持ちでお別れできること。もう一つは、身体を洗い清めることで「次の世界へと旅立つ準備を整える」という精神的・宗教的な意味合いを持つ点です。
【湯灌が故人や遺族にもたらす安らぎ】
湯灌の最大のメリットは、遺族にとって「ちゃんと見送れた」という心理的な安堵感を得られることです。身体を清める行為は、単なる見た目の清潔さだけでなく、「大切に送り出したい」という気持ちを表現する行動にもなっています。ご家族が実際に湯灌の様子を見守ることで、悲しみと向き合いつつも最期をしっかり受け止めやすくなるという声もあります。
【宗教的・文化的背景から見る湯灌の意味】
仏教の浄土思想や神道の禊(みそぎ)など、穢れを祓い清めるという考え方は日本文化に深く根付いています。そのため、湯灌は宗派を問わず広く行われることがありますが、地域や宗派によって手順や呼び方が異なる場合もあります。また、基準や作法が厳密に定められている宗教もあるため、事前に確認しておくと安心です。
各務原市、岐阜市での葬儀 家族葬はメモワール迄お問合せ下さい。

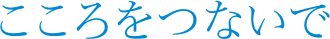
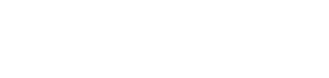

コメント